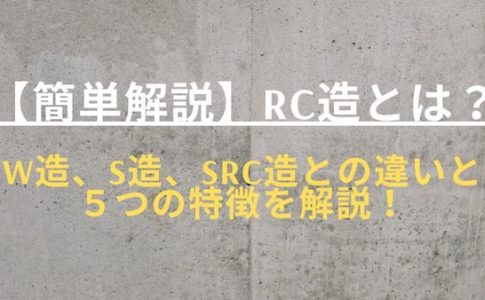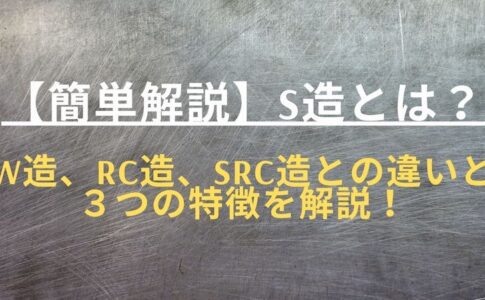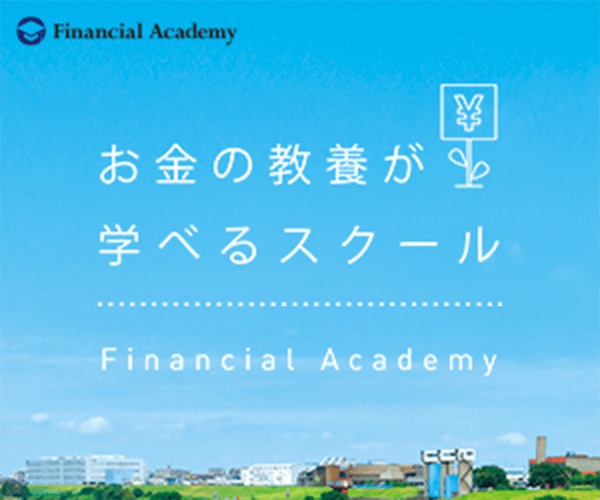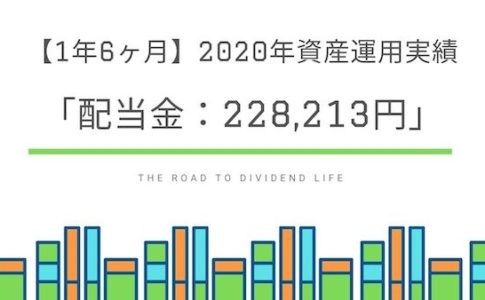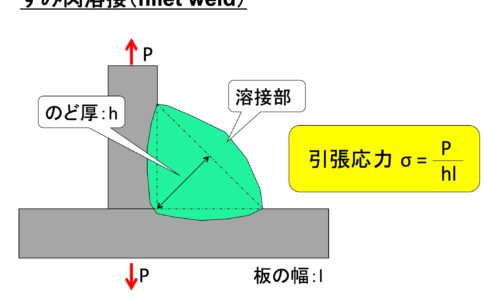この記事では、機械材料の許容応力の決め方を具体的に解説します!
- 機械材料の許容応力の決め方が具体的にわかる
そもそも許容応力とは?って人はこちらの記事を読んで見てください!
1.機械材料とは?
- 機械を構成する材料の総称
- 機械に必要な強度、特性など用途に合わせて選定する必要がある
ここでは、機械材料の中でも一般的な以下の金属材料に関しての許容応力の決定方法をご紹介してきます。
- SS400
- SUS304
- S45C
- SCM435
2.『鋼構造設計規準』による決め方
- 材料の「降伏応力」「引張強さの70%」の小さい方をF値とする
- 許容引張応力=F/1.5
- 許容せん断応力=F/1.5/√3
鋼構造設計規準とは、以前のたわみに関する記事でも登場しましたが、鉄骨等の鋼構造で構成される建築物の設計の基本とされるバイブル的な規準であり、日本建築学会が発行しているものです。
機械の設計をする上では、
- 動かない建築物の考え方をベースとして
- 動く機械ならではの要素を考慮する
が基本的な考え方になります。それでは、具体的に鋼構造設計規準による許容応力の決定方法を解説していきます。
2.1 F値の考え方

F値とは、鋼構造設計規準で規定されている指標
- 引張強さの70%
- 降伏点
の小さい方をF値と規定している!
例えば上の材料の場合、降伏点の方が小さい値を取るので、降伏点がF値となります。
一方、下記の材料の場合は引張強さの70%の方が降伏点より小さいので、引張強さの70%がF値となります。

なぜ、F値を求めるかと言うと、ここから設計で必要な許容応力を求められるからです。
この式を使うことで、許容応力は決定することができます。
ここで、
- F値≒降伏点・・材料が塑性変形しない応力
- F/1.5・・安全率を1.5倍考慮している
と考えることができます。
以前の記事で、許容応力は降伏点から安全率を加味したものを説明しました。
つまり、鋼構造設計規準では安全率1.5倍を加味しています。
- F値は降伏点、引張強さの70%の小さい方
- 許容引張応力=F/1.5
- 許容せん断応力=F/1.5/√3
- 鋼構造設計規準は安全率1.5倍の考え方
2.2 具体的なF値の計算結果および許容応力
鋼構造設計規準と各材料の引張強さ・降伏点(耐力)より算出した結果をまとめると下の表になります。

材料の引張強さや降伏点はJISや鉄鋼メーカーのカタログ等から調べることができます。
F値の考え方は、広く適応できるため、しっかり理解して是非活用ください!
3.『発電用火力設備技術基準』による決め方
- 火力発電所等のボイラーや蒸気タービンを設計する上で遵守しないと行けない基準
- 電気事業法にて、発電用火力設備技術基準の適合義務が定められている
そして、この基準の中には、各温度における許容引張応力がまとめられています。
上記リンク先中のP.102〜別表第1「鉄鋼材料の各温度における許容応力」に各材料・温度別の許容応力が記載されています。
各材料の許容引張応力を表に抜き出すとこんな感じです。

全体的に鋼構造設計規準の考え方より低めの値になっています。高温・高圧を扱う発電用の基準だから厳しめなのかもしれません。常温ではない環境で使用する場合は、確認したほうがいいですね!
- 温度ごとの許容引張応力が記載されている
- 鋼構造設計規準より厳し目の数値
4.許容応力の具体的な決定方法まとめ
鋼構造設計規準による許容応力決定方法
- F値は降伏点、引張強さの70%の小さい方
- 許容引張応力=F/1.5
- 許容せん断応力=F/1.5/√3
- 鋼構造設計規準は安全率1.5倍の考え方
発電用火力設備の技術規準による許容応力決定方法
- 温度ごとの許容引張応力が記載されている
- 鋼構造設計規準より厳し目の数値
今回、許容応力の算出に使用した参考書は下記から入手できますので、必要な人はリンク先を確認してみてください。
鋼構造設計技術規準の購入はこちらから
発電用火力設備の技術基準はHPで見れます!