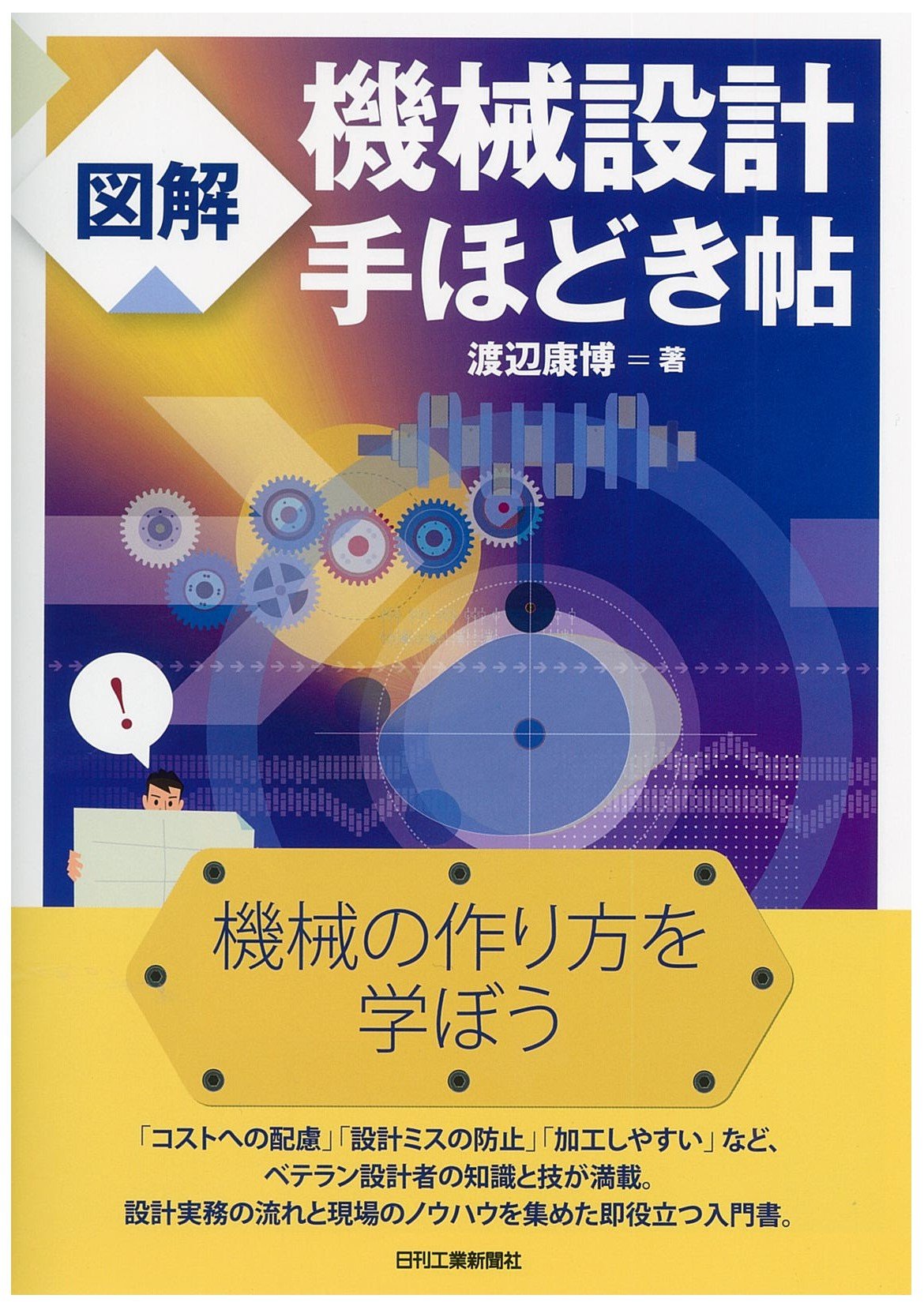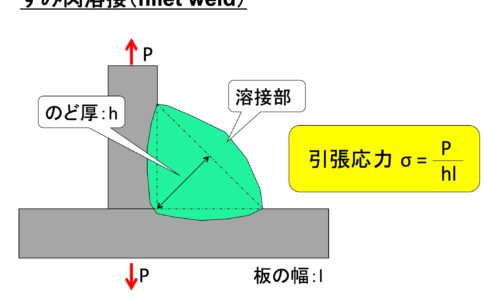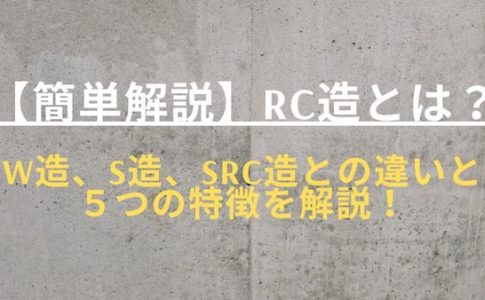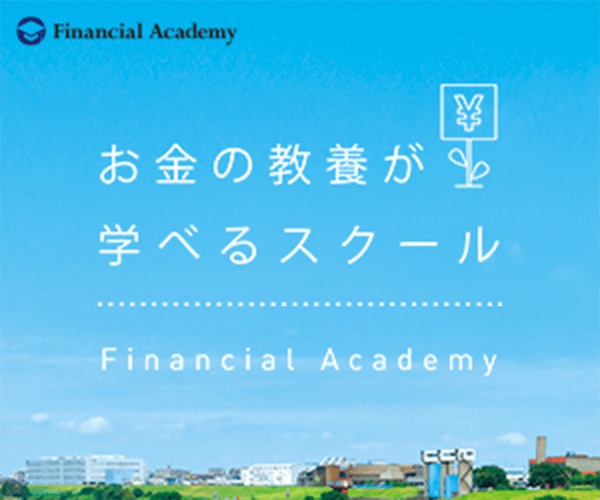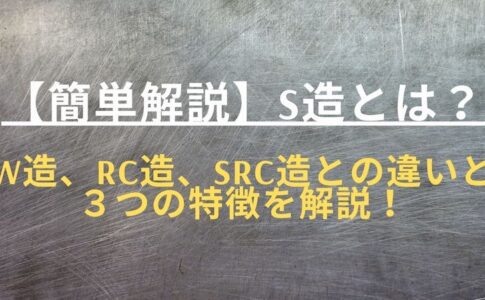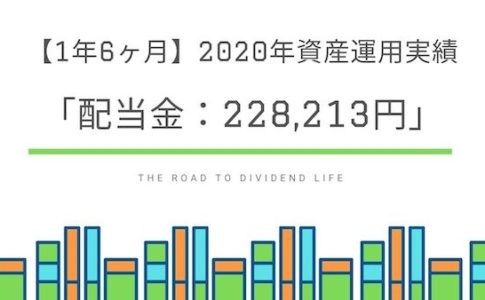この記事は、機械要素の基本であるボルト・ナット(ねじ)に関して、設計で必要な情報をまとめた記事です。
- ねじの基本知識がわかる!
- ボルト、ナットの基本知識がわかる!
- 設計する上でのPOINTがわかる!
目次
1.ねじの使い方は主に3つ
- 締付け用ねじ
- 管用ねじ
- 送り用ねじ
これら3つの用途について説明します。
1.1 締付け用ねじ

一番基本的なねじの使い方です。
ボルトとナットを使用し、締付けたい部材を挟むことで固定させます!
何かと何かを固定したいときに使う方法です。周りを見渡すとたくさんあると思います。
1.2 管用ねじ

配管同士を繋げるために使用するねじです。あんまり馴染みが無いように感じる人も大かもしれませんが、水道管にも使っています。
例えば、キッチンシンクの下、洗面台の下を覗いて見てください。配管同士を繋げるのにねじの機構を使っているのがわかると思います。
配管は内部に流体を流すので、ねじはテーパー状に切られており、漏れにくい構造となっています。
1.3 送り用ねじ

送り用ねじは普段あまり見る機会は少ないと思います。工作機械や産業用機械ではよく見るものです。
モーターによる回転運動でねじを回し、そのねじに接続している部材の前後運動に変換するものですね。
以上がねじの主な3つの用途になります。
以降では、機械設計をする上で一番の基本となる締付け用ねじ(ボルト・ナット)に絞ってポイントを説明してきます。
2.ボルト・ナットの強度

- ボルト、ナットの強度はJISに規定されている(JIS B 1051)
- 強度区分と呼ばれる値によって強度が異なる
- 強度区分は全9種類(4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9)
- 強度区分の左の数字が引張強さの1/100[MPa]
→強度区分4.6 ⇒ 引張強さ400MPa(4×100)
- 強度区分の右の数字が引張強さと下降伏点or耐力の比の10倍
→強度区分4.6 ⇒ 下降伏点240MPa(400×6/10)
- 設計するときは、保証荷重応力を使おう!
JISで規定されているボルト・ナットには強度区分と呼ばれる強度の規定があり、その数字によって保証されている強度を知ることができます。
材料の引張強さ、0.2%耐力、許容応力について詳しく知りたい人は、こちらの記事で詳しく解説しています。
強度区分は、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9の9種類あり、左側の数字が引張強さの1/100[MPa]を示しています。
例えば、強度区分が4.6の場合、左の数字は4なので、
引張強さ=4×100=400MPa
となります。
一方、右の数字は引張強度と下降伏点もしくは耐力の比の10倍を示しています。
例えば、強度区分が4.6の場合、右の数字は6なので、
下降伏点=400MPa×6/10=240MPa
となります。
また、JISには保証荷重応力と呼ばれる応力が規定されています。
これは、降伏点の90%前後に設定された応力で、実際に試験で永久ひずみが発生しないことを保障されている値です。つまり、この荷重以下ならボルトは強度的に問題ないと言えます。(※使用環境によっては強度は変化するのですべてOKではないので注意)
- 使用するボルトに作用する応力が保証荷重応力以下となるように設計しよう!
- ボルトの強度、保証荷重応力はJIS B 1051を参照
3.設計する上でのPOINT
3.1 並目ねじと細目ねじの使い分け
- 基本的には並目ねじを使用する!(コスト安い、入手しやすい)
- 組立後の緩み防止が重要な場合、細めねじを選ぶ!
- 細かい位置決めが必要な場合、細目ねじを選ぶ!
- ざっくり細目ねじは並目ねじの6倍の値段(目安)
知っている人も多いと思いますが、ねじのピッチ(山と山の間の距離)が通常より短いものを細めねじと言います。
例えば、M16のボルトなら通常ピッチ(並目ねじ)は2mmですが、細目ねじなら1.5mmです。
一般的に、並目ねじが使用されており市場に多くあり、コストも安いです。
細目ねじは、
- つる巻角が小さいので、緩みにくい
- 1回転での送り量が少ないから細かい位置決めに使いやすい
等の特徴を持っていますが、コストがおよそ6倍と割高になってしまいます。
本当に必要なところを見極めて適切に使いましょう!
3.2 最小の嵌合長さ

ねじを利用してロッド等を繋げている場合(上のイメージ)、どれだけ嵌め代が必要だと思いますか?
答えは最低でも、ボルト直径の8割(0.8d)の嵌め代が必要です。
0.8d以上なら、ネジ部でのせん断破壊より先にボルトが引張応力により破断し、0.8d以下なら、ネジ部が先に負けてしまうからです。
つまり、作用する荷重に耐えれるボルトを選定していれば、0.8dの嵌め代があると強度的に問題ないと言うことです。
実際、ナットの厚みはJISでもISOでも呼び径(直径)の0.8倍程度となっています。
3.3 ボルトの設計長さ

ボルトは基本的にナットを通してから3山程度飛び出るように長さを決めましょう。
ねじの端部は、しっかりとねじが作られていない「不完全ねじ部」が存在します。
この部分は、ねじ山が不完全なため十分な強度がありません。この部分を避けるために、3山を目安に飛び出させることで十分な強度を確保することができます。
また、長く飛び出し過ぎても邪魔なので、3山程度を目指しましょう。
- 基本的に並目ねじから選定しよう。振動による緩みを防ぎたい場合以外は、細めねじを選定しよう。ただしコストは並目ねじの6倍程度!
- ねじの最小嵌合長さは直径の8割(0.8d)!
- ボルトの長さはナットから3山出る程度に設計しよう!
4.ボルト・ナットを使った設計まとめ
- ねじの主な3用途
- 締付け用ねじ
- 管用ねじ
- 送り用ねじ
- ボルト、ナットの強度はJIS B 1051の強度区分を確認
- 使用するボルトに作用する応力が保証荷重応力以下となるように設計しよう!
- 基本的に並目ねじから選定しよう。振動による緩みを防ぎたい場合以外は、細めねじを選定しよう。ただしコストは並目ねじの6倍程度!
- ねじの最小嵌合長さは直径の8割(0.8d)!
- ボルトの長さはナットから3山出る程度に設計しよう!
【おすすめ参考書】
「機械設計手ほどき帖」と言う参考書が初心者向けにかなりわかりやすく説明されているのでおすすめです!
特に、こんな人に最適!
- これから機械設計を始める新入社員
- もう一度基本を見直したい若手社員
- 後輩への指導のポイントを確認したい中堅社員
以前の記事でも詳しく紹介していますので、気になる人は読んでみてください。